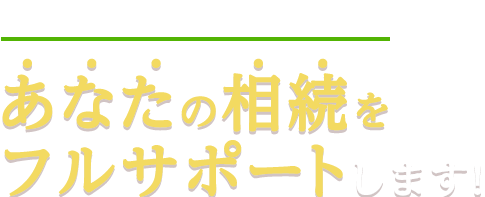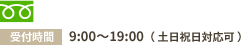相続人以外でも遺贈なら遺産を取得できる。包括遺贈と特定遺贈とは?
相続人の範囲については民法で決められているため、相続人以外の人に財産を残したい場合は「遺贈」という方法を使う必要があります。遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、それぞれ特徴があるため、事前によく理解しておくことが重要です。
そこで今回は、遺贈のやり方やポイント、注意点などについて詳しく解説したいと思います。
遺贈しないと残された人が困るケースがある?
遺産相続が発生した際に遺産を相続できるのは、民法で決められている法定相続人に限られます。そのため、次のようなケースについては遺贈などの対策をとらないと、相続が発生した際にトラブルになることがあるため注意が必要です。
内縁の妻や夫は相続できない
婚姻届を役所に提出しておらず正式に結婚はしていないものの、夫婦同様に日常生活を送っている状態を「内縁」といいます。
内縁の妻や夫には、あらゆる面において夫婦同様の扱いを受けることができますが、相続については残念ながら他人同然となってしまうため注意が必要です。
例えば、内縁の夫が亡くなって相続が発生した場合、内縁の妻は相続人になれないため、内縁の夫名義の家に住んでいたりすると、最終的には退去を迫られることになりますし、内縁の夫名義の預金口座についても一切相続することはできません。
内縁の夫側の親族と良好な関係性であれば、話し合いで解決できることもありますが、多くの場合、そのような平和的な解決は望めず、残された内縁の相手方が苦労することがよくあります。
配偶者の連れ子は相続できない
再婚している方の場合は、再婚相手に連れ子がいるケースがあります。
連れ子については、長期間同居して家族同様に生活をしていたとしても、自分の相続における相続人にはなれません。
連れ子にも財産を残したい場合は、養子縁組をするか遺贈によって遺産を取得させる必要があるのです。
子がいる場合、孫は相続できない
自分が亡くなって相続が発生した際に、子が存命の場合、孫は相続人にはなれません。(子すでに亡くなっている場合は、代襲相続によって孫が相続人になれます)
そのため、子がいる状態で孫にも財産を残したい場合については、孫と養子縁組をするか、遺贈によって遺産を取得させる必要があるのです。
孫に遺産を取得させることができると、一代飛ばして財産を移転できるため、相続税の節税に繋がるため、よく用いられることがあります。
このように、比較的亡くなった本人に近しい人物だとしても、何の対策も講じていないと一切の遺産を取得することができないのです。
遺贈のやり方と種類(包括遺贈と特定遺贈)
遺贈とは、遺言書によって任意の人に遺産を取得させる方法で、親族に限らず友人、知人など誰にでも遺産を取得させることが可能です。よって、上記のようなケースでは必ず遺言書を作成する必要があるということになります。
また、遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つの種類があり、効力が若干異なるため違いについてよく理解しておく必要があります。
包括遺贈とは?
包括遺贈とは、相続財産の一定割合を遺贈することで、具体的には以下のとおりです。
- 相続財産の半分を○○に遺贈する
- 相続財産の1/3を○○に遺贈する
このように、遺贈する対象となる財産を特定することなく、割合だけを指定します。
包括遺贈のポイント:包括遺贈は相続人と同じように扱われる
包括遺贈を受ける人のことを「包括受遺者」といいます。包括受遺者は民法の以下の条文によって、相続人と同等に扱われることに注意が必要です。
民法第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する
よって、包括遺贈をすると包括受遺者については遺産分割協議に参加して、他の相続人と同様にどの財産を取得するのかについて話し合わなければなりません。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても指定された割合で負担する義務が出てくることにも注意が必要です。そのため、借金の相続を放棄したいのであれば、相続人と同様に家庭裁判所において3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
※包括受遺者がすでに亡くなっていたとしても代襲相続は発生しません。
このように、一部については相続人とは別の扱いを受ける部分もあるため注意が必要です。
特定遺贈とは
特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に特定して遺贈することで、具体的には以下のとおりです。
- A銀行の預金債権を○○に遺贈する
- Bアパートを○○に遺贈する
特定遺贈については、包括遺贈とは違い相続人と同様の扱いは受けないため、遺産分割協議に参加する必要はなく、特定された財産を受け取るだけです。また、マイナスの財産についても義務はなく、放棄する場合も家庭裁判所での手続きは不要で、期間の制限もありません。
特定遺贈のポイント:特定する財産は正確に記載する
特定遺贈の場合は、特定する財産を明確に特定することが重要です。
特に不動産の場合については、郵便などを送る際に記載するいわゆる住所ではなく、登記簿に記載されている地番や家屋番号を調べて記載する必要があります。
また、相続が発生した段階でその特定された財産がすでに無くなっていると、特定遺贈自体が無効になってしまい、受遺者は遺産を受け取ることができないため注意が必要です。
一方、包括遺贈のように割合だけ指定する形であれば、そのような問題はありません。
受遺者にも相続税が課税される
遺贈する際には、受け取る側の相続税にも注意が必要です。
相続税は、相続人にのみ課税される税金ではなく、遺産などを受け取った人に対して課税されるため、遺贈を受けた場合も基礎控除を超えると相続税が課税されます。
そのため、現預金以外の財産を遺贈する場合は、受遺者の納税資金についてもあらかじめ対策を講じておく必要があるでしょう。
また、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)以外の人が相続によって財産を取得した場合については、相続税が2割加算されることにも注意が必要です。
遺贈するなら、当事務所までまずはご相談ください
法定相続人以外の人に財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成して遺贈する必要があります。
ただ、包括遺贈か特定遺贈かによって、受遺者にかかる権利や義務が違ってくるため、どちらの方法が適しているかについては、相続人や相続財産を詳しく調査した上で検討することが大切です。
当事務所はこれまで多くの相続関連のご相談に携わっており、さまざまなケースを経験しておりますので、弁護士ならではの視点で的確にアドバイスいたします。また、同じ事務所内に税理士もおりますので、遺贈による相続税の負担についても事前にシミュレーションすることが可能です。
初回相談は60分無料(平日のみ)で対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。